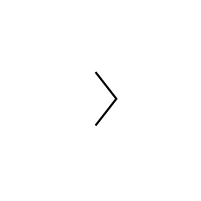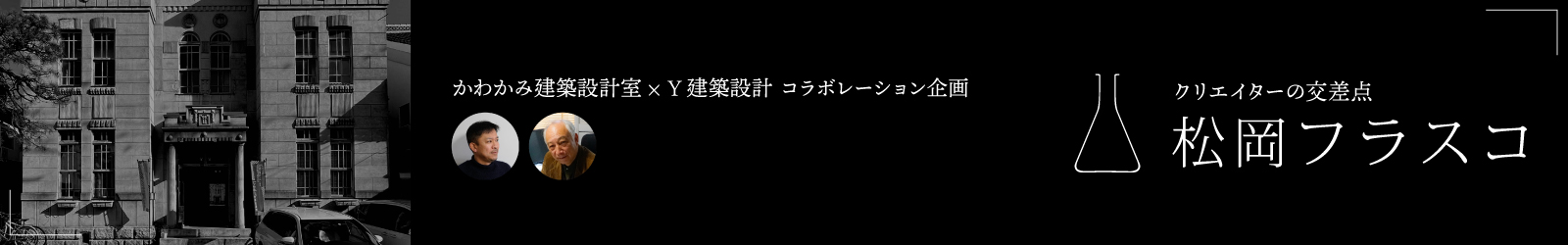その1 民家は差別用語であった?
民家とは古くて立派で逞しい住まいと思われがちだが、
江戸時代に始まる用語で、実は武士が『お屋敷』と区別した庶民の住居で農家・町家・漁家などのことで、質も規模も価値が低いとみなされた住居の事を指した。
それは士農工商の身分制度の中で、武士から見ると低い地位の差別用語であった。
現在の民家のイメージは庶民の住まいで『古民家』のことを指し、
およそ戦前までに建てられた立派で伝統的な住居と思われているが、
当初はそうではなかった。
確かに庶民の住まいは、主に煮炊きのできる家畜小屋の様で造りも粗末なもので、
土間に茅葺きの屋根が掛かっただけの隙間だらけで寒くて暗い棲家であった。
明治以降は差別もなくなりその稼ぎによって盛んに造られ続け、質も量も飛躍的に上がったが
古民家といえる質の高いものは明治中期から戦前までの僅かに80年ぐらいの時期だけであり、
敗戦後はまた殆ど出来なくなった。

戦後80年となった今でこそ古民家はかなり質の高いイメージで特別な価値があると見られ、流行にもなって、利活用されてきた。
逆に特別視され差別化されている。
意外にも外国人に高く評価され、再生の依頼を受けることが多くなった。
我々日本人こそその価値を再認識し、誇りを持って積極的に利活用して欲しいものだ。

ちなみに古民家の再生工事は特別でかなり高額と思われがちだが、
意外にも新築以下の工事費で出来る。
その木材を再利用して別の敷地に建てるという『移築』でもほぼ新築並みの費用で出来る。
昨今の民家再生は安価で上質で特別な価値があり、逆に差別化できる行為かと思われる。
川上