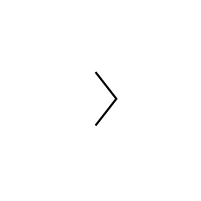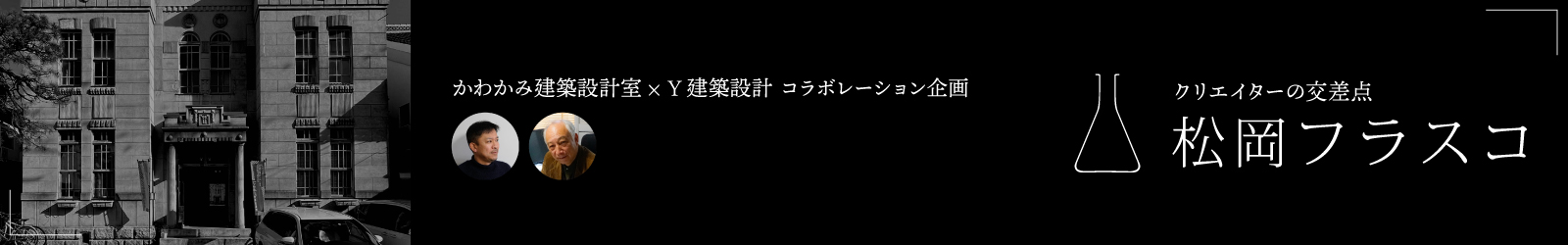その5 民家は粗末な材で無駄なく造られた。
木造の民家はそのほとんどが大きくて立派な木材をふんだんに使って建てられていて庶民には手に届かない贅沢普請だと思われている。
それは全く逆である。
民家に使われている木材を見ると、曲がっていたり割れていたり節があったり、
中には何度も使い回された古材も利用したりして丁寧に作られている。
もちろん木材はその殆どが地元材で外材は使われていなかった。
例えば民家再生の工事を進めていくとどのくらい材を大切にしていたかが判る。
家づくりでは沢山の柱が必要になるが、
中には節があったり曲がったりしているが、お座敷に使うものはなるべく節のないものを選んで綺麗な面を出して、大工さんは丁寧に仕上げた。
節があったり割れていたりする材は土間やかってに使ったりした。
曲がった梁や桁は木の皮だけを削り落とし、できるだけ木の持っているクセをそのまま活かして組み合わして使っている。手間もかかるが強い。薄暗い土間に入って見上げると逞しい梁組がそのまま見えて見事と言うしかない。

今はクセのない真っ直ぐな外材を多く使っていて、他は捨ててしまうから勿体無いし、そもそも弱いし味もない。
外材は以前は安かったが流通事情によってかなり高価になってきた。
今は内地材が安くなり、質のいいヒノキや杉がふんだんに使える。
壁土もそうだ。
近くの土を掘って寝かせて藁を混ぜて時間をかけて作り、それを左官屋さんが丁寧にコテで塗る。
漆喰塗りは実は世界中にあるが、仕上げの丁寧さは日本が群を抜いている。で、いつまでも強くて美しい。
日本の土蔵の壁を見れば、構造的な割れが無ければ100年そのままで汚れない。
メンテナンスが要らないのである。ペンキや吹付ではそうはいかない。

木製の窓もこの時代に合わせて断熱や気密を考慮して作れば長持ちだ。
現に我が事務所は築100年を越すが窓やドアは木製の手作りで健在である。果たして樹脂サッシは大丈夫なのか?。

かつては全てがごく当たり前の材を当たり前に使い、普通に造っていたのである。それらは時間が経てば味わいを増し、さらに魅力的になる。
そもそもこの国の民家は高級でも贅沢普請でもない、ごく普通の家だった。
日本人が誇りの持てる普通の造り方だったのである。もう一度戻りたいものだ。
川上