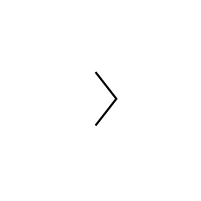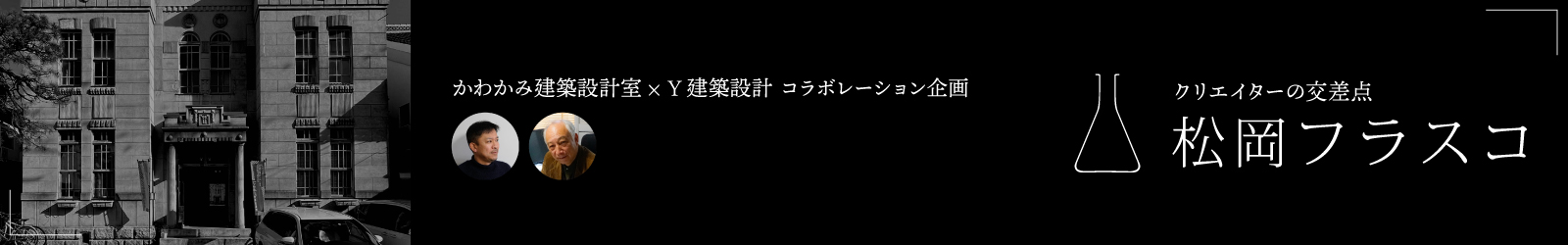その4 民家は狭かった?
一般的に民家は大きく立派だと思われているが果たしてそうか?。
今の時代住宅は生活のためにだけの目的で造られているので床面積の目安は一人10坪。
たとえば4人家族ならせいぜい40坪ほどでいいことになる。
その昔民家では様々な機能があってそれを満たすには床面積100坪という大きな家になったが
それでも狭かった。
民家は基本的には平屋でそこに大家族で住んでいて、現代の様な核家族のための家は造れなかった。
まず親世代、若夫婦やその兄弟、数人の子供やお手伝いさんなど10人ほどが同居していた。家の中には馬や牛もいて、外の小屋には山羊や豚や鶏もいた。
主屋の大戸を潜ると広い暗い土間があって、そこでは筵や俵の藁細工造りの作業スペースがあり、横には馬屋が付いていて、その上には藁や豆殻などが餌として置かれていた。
馬屋の反対側には土間を挟んで囲炉裏のある「おえ」という広い板の間の居間兼食堂があった。
その他は親の部屋である小座敷だけは独立してあったが、後は皆で寝る寝間と納戸や小屋裏と広いお座敷だけだった。
お座敷は普段は使うことができず、自宅で執り行われた冠婚葬祭の際にのみ使われた部屋だ。
冠婚葬祭のセレモニー時には100人程の親類縁者が集まったので二間続きのお座敷には入りきれず建具を取り払って家具も片付け、隣のオエや土間も使って接待をした。

お台所もスペースは足りず、家の外まで使うしか無かった。
もちろん子供達も部屋は無く、あっても屋根裏の暗く狭い所に追いやられていた。
ほぼ8人が3部屋に寝起していて、皆狭い所を移動したりして暮らしていたのである。
当然プライバシーは無かったが、お互いの気遣いは多々あった。
その様子が今でも分かるのはお寺である。狭いスペースを建具で仕切っている「間」の使い分けが見事であるが説明は省く。
とにかく今これらの機能を満たすには家畜のスペースは無くとも
恐らく床面積300坪の家が必要だろう。それは不可能である。
とするなら狭い所を広く使うには茶の間はどうだろう?。

例えば4畳半の茶の間ならそこに家具を持ち込めば少なくとも5つ以上の機能がある。
居間・食堂・客間・寝間・書斎などとして多機能で稼働率が高いのである。
畳の床に座り、ちゃぶ台や布団を敷いて狭いところを不便なく使う快適性。
つまり日本人ならではの快適感を取り戻せるのではないかと・・。
最近は外国人の方がその事をわかっている。
ここに至り民家は狭かったがそれ程不便は感じなかったようだ。あの時代が懐かしく、豊かであったとさえ思われる。
とするならもう一度かつての民家に本気で向き合ってみるのもいいかと思う。
新しいことばかりが進歩ではなく、
住まう原点この国の住まいのカタチを求めて。
川上