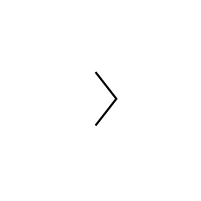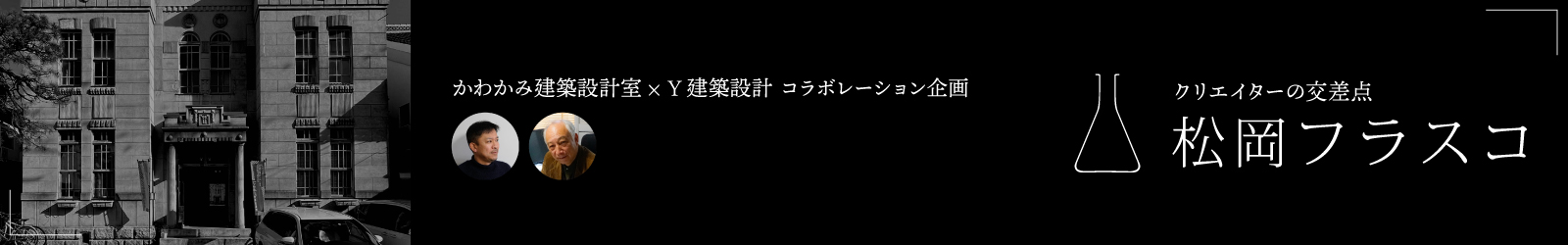その3 民家は無意識で個性が無かった
住まいはいつの世も自然条件と社会条件の二つで構成されている。
民家は特にその地域の自然条件(風水害、日射、生物など)に大きく左右され、全国的には多様で固有の形態があるが、その地域では何々造といってほぼ同じ形態であることが多かった。
今は通勤にいいとか買い物が便利とか病院が近いとかという社会条件の方が重要視され、それでできることが多い。


ところでかつて人が住まいを造ったり直すことを普請すると言った。
先ずは自然条件に逆らわずに造られ、それが一旦出来ると大切にされ、少なくとも親子3代(約100年)が壊れるまで使って壊すことはまず無かった。
社会条件でいうとまず結婚や出産で家族が増えると多少の増改築はされたがほぼ原型をとどめていて、
士農工商の身分制度もあるが、生産や生活の仕方はどの家も継承され昔と余り変わらなかった。
故に普請する場合には間取りもほぼ決まっていて敢えて変える必要もなかった。
普請する行為は一大事ではあるが、今までと同じ間取りでよかった。



ところで民家の間取りは大きく土間と板の間とお座敷の3つに分かれ、どこも同じであった。
その中にも接客と日常生活の区別があり、いわゆるハレとケという価値観は皆同じに貫かれていた。
他人とは変えたいとは思わず、個性もなかったが、そこには豊かで尊い文化が流れていた。
敢えて違う点を探すと、心意気と材と技と規模のみである。
当時の民家は今の時代とは全く違った意識で造り使われていた。
翻って今は個性を磨こうという時代で、人と同じ事をしない様に教育されてきて、
住宅も様々な個性的な住まいが出現している様だが、
マンションやハウスメーカーの住まいが結果的にはどれも同じに見えるのは皮肉な事である。
昔の民家を調べると、形態や思考は同じであっても、住む人の性格や容姿は多分に個性的であったことがわかる。
その点同じ制服を着た学生の方がそれぞれ個性的であるのと似ている。
ここに至り今後の住まいはどうあるべきかと考えるに、
昔の民家に倣い、『令和の民家』が出来ないものかと思っている。
翻って、一億総中流で共稼ぎで情報の時代は果たして個性的な人間と生活が可能かと疑われる。
人並みの生活を目指す方が逆に人並み以上の幸せと安心が可能ではないかと思う。
つまり無意識に個性もない『令和の民家』という家づくりもいいのではないかと思う。
これからの時代は建築基準法も厳しくなったり工事費も高騰し、沢山の制約の中で普請をしなくてはいけなくなった。
目指す『令和の民家』の道は遠いが、今までの様にこの道を進んで行くことにしている。

川上