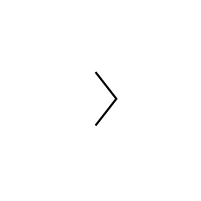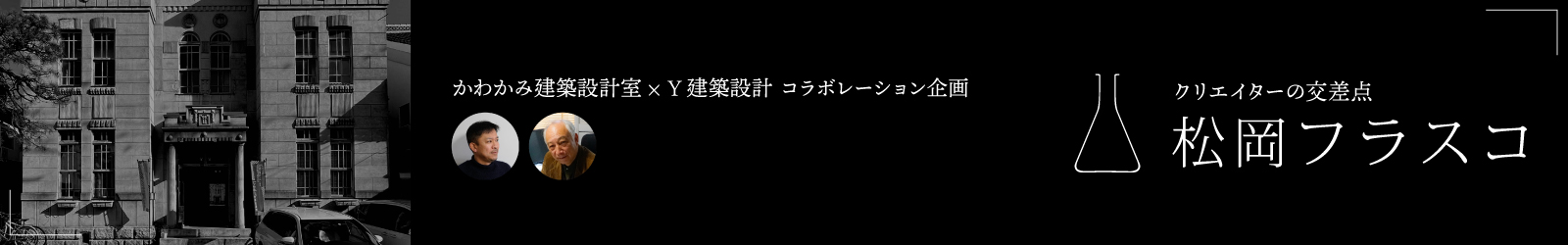その2 民家は人様の為に造られた?
今でこそ数が少なくなっているが、古民家は概ね立派で大きい。
昔の建物はその殆どが平家に屋根が架かっていて、間取りは主に土間・板の間・お座敷の3つのブロックに分かれていた。そこでの生活は主に家族の寝食・生産・接客であり、とりわけ接客の為の造りが普段の生活空間と区別され広くて立派であった。
勿論土間や板の間も丁寧に造られていたので今時の質を遥かに超えているが・・。



当時お座敷は家族でも出入り禁止の最高の応接間でもあった。
奥に設えられた下座敷・上座敷の二間続きは書院造りで、正面の床の間と床脇と付け書院が、縁側の外は手入れの行き届いた定番のお庭が客を迎える。子供の頃、そこに脚を踏み入れると祖父に叱られた。

詳しく見れば使われている柱や長押などの木材も、職人の技も手間も特に素晴らしい。佇めば思わず襟を正す。ここは主に冠婚葬祭などの晴れの場として頻繁に使われていた最高の日本式ビップルームであった。また最も大切で必要不可欠なスペースであった。
この場を造り・備え、もてなすことが普段暮らすことより大切だと確信していた。
極端に言えば家長はその為に働いて一人前と認められることを生き甲斐とした。
ハレの場を求めて。見栄もあっただろう。
逆に言えば自分達のためよりも、人に喜んで貰えることが最も大切な価値だった。

この事を見直そうと言うのではない。人が訪ねてくることが極端に減った今の時代、おもてなしの仕方も戸惑う様になってきた。
これからは当然自分達の幸せの為に家造りを目指すべきだが、
可能なら、僅かでもヒトに喜んで貰えるスペースを考えたい。
またそこに古民家が残っているならこの貴重な空間をなんとか別の価値としてでも活かすことができないかとも・・。
ついでに逞しい梁組の吹き抜けの土間や板の間も、そして屋根裏も活かしたいものだが・・。
川上